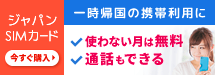Hello The Japanese School : Seasonal Events at the Japanese Language Supplementary School (April, 2021)
01 Apr 2021

本校では、日本の伝統文化を体験的に理解できるように四季折々の行事を教育課程(年間指導計画)の中に組み込んでいます。この活動を通して、日本語学習の普及と日本の伝統文化への理解を促進することを目指しています。
<伝統文化の活動事例>
5月 こどもの日集会
こどもの日と菖蒲の葉について考えます。
「こいのぼり」の歌を歌います。
7月 七夕集会
七夕の由来と夜空の星について考えます。
「たなばたさま」の歌を歌います。
10月 お月見集会
お月見とお団子やすすきの飾りについて考えます。
日本人会「箏の会」の演奏を聴きます。
11月 書道
書き初めの由来や筆の持ち方について考えます。
「とめ・はね・はらい」について習い、「水書」を体験します。
2月 節分集会
節分と豆まきについて考えます。
「まめまき」の歌を歌います。
2020年度は新型コロナウイルス(COVID-19)禍にあり対面授業の開始が8月末になりましたが、このような状況の中でもなんとか子どもたちに日本の伝統文化に触れてほしいという思いで本校が行った四季折々の行事のいくつかを紹介いたします。
お月見集会
2020年は10月1日が中秋の名月だったそうですが、本校では10月10日にお月見集会を行いました。目的はお月見の由来を知り、日本の伝統文化に親しむことです。
当日は日本人会の「箏の会」の方に来ていただき、お月見に関する箏(琴)の演奏をしていただきました。今回はコロナ禍にあって大勢の児童生徒を1カ所に集めることができないため、小学1年生だけの参加となりました。その1年生の参加態度はしっかりと椅子に座り、お月見の由来や箏の演奏を最後までよく聴いていました。その姿はとても立派で感心しました。その他の学年については、箏の会の演奏をビデオ収録したものを10月17日にお月見行事学習として鑑賞しました。また、全校児童生徒にお月見の雰囲気を少しでも感じてもらうため、団子を配りました。
お月見集会で聴いた箏の演奏は、心が穏やかになりとても楽しいひとときとなりました。日本人会「箏の会」の皆様に心より感謝申し上げます。

箏演奏「月」
箏演奏とお話「もどってきた勘太」

校長からお月見集会のお話を聞く

校長から箏の会へ御礼の言葉と花束贈呈
書道
12月5日と12日の2日間で児童生徒の全員が、水書による書道体験を行いました。
小学校学習指導要領の改定に伴い、2020年から小学校1・2学年の書写の授業に水書用筆等を使用した運筆指導が取り入れられました。また、下記の様な利点がありますので、全校で水書体験をすることとしました。
①墨ではなく水を使うため、服や部屋を汚す心配がなく、準備・後片付けも簡単にできます。
②毛筆で書くことにより硬筆では体感しにくい「とめ・はね・はらい」の感覚を理解し、意識することができるようになります。
③乾けば文字が消え、何度も繰り返し練習することができるので、正しい運筆が習慣化し、身につきます。
書道体験では、初めに、「書き初め」の由来を知り、書くときの姿勢、腕の使い方、筆の持ち方を習った後に、水書の体験をしました。水書では、「とめ、はね、はらい」に注意しながらお手本をよく見て字形よく書くこととしました。学年のめあては次の通りになります。
小1・2年:姿勢や用具の持ち方に気をつけ、丁寧に書く。
点画の長短、接し方、交わり方に注意して筆順に従って正しく書く。
小3・4年:文字の組立て方に注意して、文字の形を整えて書く。
文字の大きさや配列に注意して書く。
小5・6年:点画の筆使いや文字の組立て方を理解しながら字形を 整えて書く。
字配りよく書く。
中 学 部:字形、文字の大きさ、配列、配置などに配慮し、調和よく書く。
この書道体験後に、本校児童生徒が家庭で取り組んで書き上げた作品は、1月1日〜1月14日に行われた日本人会書き初めに出品し、日本人会会館の2階(アトリウム)に展示していただきました。



書道体験

日本人会書き初め展
節分行事学習
1月31日の遠隔授業時に、校長作成の動画を視聴して節分の由来や節分に豆まきをする意味を学びました。
また2月6日には、小学部1年生・2年生が豆まき体験をしました。児童は元気よく声を出して、鬼めがけて豆を投げていました。きっと今年も元気な体で、しっかりと勉強することができるでしょう。今回使用した豆は、発泡スチロールでできており、鬼のお腹についている箱の中に入った豆の個数で得点を競いました。


節分 豆まき
海外で暮らす子どもたちにとって、当然のことながら日本で行われている伝統文化的な行事への参加はできにくい状況にあります。しかし、日本の伝統文化は数多くあり、古くから日々の暮らしの中に息づき、世代を超えて継承されてきています。
新年度においてもコロナ禍による行事開催の難しさは続くことになりますが、その伝統文化を体験(学習)することで、少しでもその奥深さや魅力について触れ、「日本の心」を体感してもらえたらと考えています。
文責・写真:日本語補習校授業校 校長 熊谷高弘